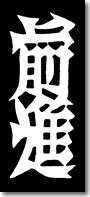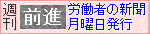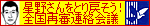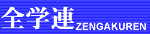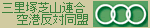『資本論』に挑戦しよう ヨハン・モスト原著『資本と労働』を学び 資本主義社会の仕組み暴き労働者自己解放の道照らす 畑田 治
『資本論』に挑戦しよう ヨハン・モスト原著『資本と労働』を学び
資本主義社会の仕組み暴き労働者自己解放の道照らす
畑田 治
全世界で労働者階級が立ち上がっている。資本主義は「死の苦悶(くもん)」にのたうっている。ヨーロッパは巨大なゼネスト情勢だ。そうした中で、マルクス『資本論』が青年労働者・学生の心を再びとらえ始めた。『資本論』が労働者・学生に読まれる時代、それは〈嵐の時代〉〈革命の時代〉だ。このたび『資本論』学習テキストとして、ヨハン・モスト原著/新訳『資本と労働』が新訳刊行委員会から発行された。この本を手がかりに『資本論』に挑戦しよう。それは階級的労働運動—プロレタリア革命の強力な武器となる。
第1章 マルクスが心血を注ぎ完成させた「革命の書」
第1節 餓死とストライキ
『資本論』第1巻が出版された1867年頃はどういう時代だったか。ヨーロッパ、イギリスで資本主義の発展が頂点に近づいていたが、それは同時に資本主義の矛盾が全面的にあらわになる過程であった。1864年に、世界初の労働者の国際組織、国際労働者協会(第1インターナショナル)が設立された。その創立宣言には次のように書かれている。
「人を酔わせるこの経済的進歩の時代に、餓死はイギリス帝国の首都ロンドンで、ほとんど名物の一つに数えられるほどになった」「いたるところで労働者階級の大多数は、彼らの上に立つ人びとの社会的地位が高まるのと少なくとも同じ割合で、低い深みに沈んでいった」
まさに資本主義の発展が、労働者階級を一層の貧困にたたき落とす過程が進行していたのである。これに対して、労働者階級はけっして黙っていなかった。資本家に対して怒りを爆発させ、ストライキ、暴動に立ち上がっていた。その闘いは嵐のようにヨーロッパ大陸を席巻した。1848年の革命の敗北でいったん後退したプロレタリアートの闘いは1860年代に再びよみがえり、その中で第1インターナショナルが結成された。
「ヨーロッパ大陸では、このところ、ストライキがほんものの伝染病のように猛威を振るい、賃上げを要求する叫びがいたるところに上がっている」(『賃金・価格・利潤』、1865年)
ストライキは大陸からイギリスやアメリカにも広がった。1869年にはベルギーの製鉄所と炭坑の労働者がストライキに入った。資本家はこれに軍隊を差し向け、多くの労働者が殺され、傷つき、逮捕された。第1インターナショナルは「ベルギーの虐殺」を徹底弾劾し、連帯と救援のカンパを呼びかけた。
「プロレタリアートのブルジョアジーに対する闘争は、その存在とともに始まる」(『共産党宣言』、1848年)
まったく、そのとおりだ。労働者階級はどんなに弾圧されても闘いをやめることはない。偉大な勝利と無念の敗北を繰り返しながら前進し、今日まで継続している。この事実そのものが、資本主義社会が矛盾をいっぱい抱えた歴史の通過点にすぎないこと、労働者階級が自らを解放するためには資本主義を打倒しなければならないことを示している。(ブルジョア国家の暴力と資本主義社会の存立は不可分一体だ。経済的論理だけで資本主義社会が成り立っているわけではない)
第2節 第1インターと共に
『資本論』第1巻が発刊されたのはこのような時代だった。マルクスは「創立宣言」を起草するなど第1インターナショナルの重要な仕事を担いつつ『資本論』第1巻を完成させた。だから、『資本論』は国際プロレタリアートの流血の闘いと一体の書だ。マルクスは第1巻の扉に「忘れられないわが友、勇敢で誠実で高潔なプロレタリアートの前衛ヴィルヘルム・ヴォルフに捧げる」と記した。ヴォルフは1848年の革命をマルクスとともに闘い、その後も弾圧と闘いながら労働者階級の組織化に一生を捧げた革命の闘士だ。
強調したいことは、『資本論』はいわゆる学術書ではない、闘いの書だということだ。そこには多くのプロレタリアートの血が流れ、革命への熱い思いが込められている。そこではマルクスの筆を借りてプロレタリアートが叫んでいる。プロレタリアートが資本主義社会の搾取の構造を暴き、ブルジョアジーを激しく弾劾し、革命を呼びかけている。だから、労働者がこれを読んで、理解できないことはない。
21世紀の私たちの世界はどうか。ILO(国際労働機関)の発表でも世界の雇用人口の45%、14億人が、1日2㌦以下で暮らす「ワーキングプア」だという。世界の資本家階級は、このように労働者から搾り取っている。マルクスの時代と何が変わったのか? 『資本論』は鋭く現代の世界を告発している。
マルクスは、自分の生命のエネルギーのすべてを注ぎ込んで『資本論』を書いた。ようやく第1巻がまとまって、その原稿が出版社に送られた直後に友人あての手紙でこう述べている。
「この著作のために私は健康も人生の幸福も家族も犠牲にしてきたのです。……もし人が牛のようなものでありたいと思えば、もちろん人類の苦しみに背を向けて、自分のことだけ心配していることもできるでしょう。しかし、私は、もし私の本を少なくとも原稿としてでも、完全に仕上げないでくたばるようなことがあれば、本当に自分を非実際的だと考えたでしょう」(1867年4月17日付、ジークフリート・マイアーあての手紙)
30年間のマルクスの理論的探求の全成果が、『経済学批判』(1859年)を経て『資本論』に結実した。マルクスは、自分の命と引き替えに『資本論』を著した。だから、私たちは真正面から『資本論』と向き合い、格闘すべきだ。それほどの価値がある。
第2章 搾取を目的として生産を行う転倒した社会
第1節 「労働者階級の理論」
労働者階級は『資本論』で自分の理論、「労働者の理論」を持ったのだ。このことは労働者階級が、資本家階級と闘って真に勝利できる力を獲得したということだ。
マルクスを全面的に支えたエンゲルスは『資本論』第1巻英語版序文(1886年)で次のように言っている。
「『資本論』は大陸ではしばしば『労働者階級の聖書』と呼ばれる。この著作の中で到達された諸結論が……日ごとにますます労働者階級の大きな運動の基本的な原理となりつつあること、どこでも労働者階級はますますこれらの結論のうちに自分の状態と大きな希望の最適の表現を認めるようになっている」
だが、その後の歴史を見ると、本来労働者のものである『資本論』が肝心の労働者から遠ざけられてきたきらいがある。労働者が「『資本論』こそ自分たちの聖書」として読んできたとは言い切れない歴史と現実がある。
また日本共産党スターリン主義は、「暴走する資本主義から節度ある資本主義へ」「大企業は敵ではない、共存する」と言い、それがまるで『資本論』の結論であるかのような主張をしている。だがそんなものは、銀行家を「大盗賊」と弾劾したマルクスの革命的精神とは縁もゆかりもない。日本共産党議長・不破哲三は『資本論』をテーマに学者ぶった議論を展開しているが、その作業はすべて『資本論』の革命的核心を解体し、資本主義と共存できるものにするための反革命的な作業だ。労働者階級を革命から遠ざけるためにやっているのだ。
ニセモノのマルクス主義や一切の体制内労働運動と対決し、『資本論』を労働者の手に取り戻そう。転向スパイ集団=塩川一派を打倒し、階級的労働運動の大前進を切り開こう。
第2節 社会の常識と闘って
『資本論』にはどのようなことが書いてあるのか。
『資本論』でマルクスは、資本主義社会が労働者階級から搾取することで成り立っていることを暴き出した。資本主義社会が剰余労働の搾取を唯一の動機・目的として社会的生産が組織される、実に転倒した社会であることを暴き出した。この社会では、労働者階級はすべての生産手段を奪われているがゆえに、自分の労働力を資本家に切り売りする以外に生きられないのだ。
当時のブルジョア経済学者は、資本家・地主・労働者はそれぞれ資本・土地・労働を持ち寄って生産を行い、その役割に応じて収入を受け取るのであり(「三位一体の定式」)、そこには、なにひとつ問題はないという主張を行っていた。それは、資本家や地主の利益に合致する理論だった。彼らは、“労働者が貧しいのは食糧生産の伸びよりも労働者の人口増加が多いからだ。だから労働者は産児制限をしろ、そして勤勉に働け、そうすれば労働者の取り分も増えて生活は豊かになるぞ”というような資本主義擁護論を振りまいていた。(今の連合中央の「企業は労働者のがんばりに見合った成果配分を」というのも、基本的にこうした主張と変わらない)
マルクスはブルジョア社会の「常識」にまでなっているこうした資本主義擁護論と徹底的に対決した。剰余労働が搾取される秘密を解き明かし、労働者が受け取る賃金は生産物の分け前ではなく労働力商品の代価であること、それは労働者がかつかつに生きていくだけの「えさ代」でしかないこと、資本家は労働者の必要労働(賃金分)以上に労働者を働かせ、その剰余労働を搾取すること、したがって資本家の利潤も、土地所有者の地代も、その根源は労働者の剰余労働にあること——こうしたことを鮮やかに暴き出したのだ。
商品価値の実体が労働であることを見抜いたのはマルクスが初めてではないが(古典派経済学)、労働力の商品化をつうじて剰余労働が搾取される仕組みを解明したのはマルクスが初めてだ。
さらにマルクスは、プロレタリアートがストライキや暴動に立ち上がっている事実を背景に、プロレタリアートこそ資本主義をひっくり返す主体であり、革命的階級であることをはっきりさせた。資本家は、今の社会はすべて自分たちが仕切っているかのように振る舞い、「資本主義よ、永遠なれ」という神話にしがみつくが、実際にこの社会を動かしているのは労働者なのだ。労働者が働くことをやめれば、資本主義社会は完全に止まる。資本家は労働者に寄生して搾り取っているだけであり、労働者階級が団結して闘えば必ず資本家階級を打倒し、階級のない共同社会をつくりだすことができる。『資本論』はそのことを、圧倒的な迫力をもって労働者階級に説いている。
『資本論』の中身は140年たった今もけっして古くない。逆に世界大恐慌の時代だからこそ、生き生きと私たちに迫ってくる。
第3章 労働者のために第1巻のダイジェストを作る
第1節 監獄の中で執筆
『資本論』は第1巻だけでも大部であり、労働者にとって読みとおすことは確かに一苦労だ。それでも、どれだけ時間がかかろうとも読み通す価値がある。マルクスは、誰よりも「労働者に読んでもらいたい」という思いでこれを書いた。
『資本論』を読み進める手がかりになるのがヨハン・モスト著『資本と労働』だ。この本は『資本論』第1巻の分かりやすい要約だ。モストはドイツ社会民主党の活動家だった(注参照)。
1860年代、ヨーロッパで労働者のストライキが各地で闘われた。闘争は時には暴動となって爆発した。71年3月、普仏戦争のさなかにパリの労働者が蜂起し、パリ・コミューンを樹立した。マルクスはこれを「史上初のプロレタリア独裁」と積極的に意義付けた。コミューンは資本家の軍隊の襲撃で72日間で敗北したが、コミューンの衝撃はヨーロッパの全資本家階級を震え上がらせた。第1インターナショナルは「パリ・コミューンの首謀者」と見なされ、各地で弾圧された。ドイツでも反動の嵐が吹き荒れ、モストは72年9月(26歳の時)、反戦デモを組織して逮捕された。
モストは73年2月から8カ月間投獄されたが、『資本論』第1巻を読んで圧倒的に感動していたモストは、これを労働者の中に広めたいと、投獄の機会にノートを取り、『資本論』のダイジェストをつくった。出獄後それを『資本と労働——マルクス「資本論」のわかりやすいダイジェスト』という表題で出版した。
モストは、マルクスだからといって絶対視しない。自分は労働者だという意識を強く持って、「これは大切だ」と思ったところをズバリと抜き書きした。読んで理解できないところは、ほかの労働者も分からないだろうと大胆に省いた。そして、モスト自身の考えで第1巻全25章を12の表題(章)に整理してダイジェストをつくった。
モストは「はじめに」で『資本論』の意義を次のようにまとめている。
「カール・マルクスの『資本論』が出版されて、近代の社会主義は確固とした基礎を、無敵の武器を手に入れた。この著作は、どんな社会も、個人が案出したいろいろな計画にしたがってつくりだされうるものではないということを明らかにしているので、たしかにすべての楽観的な幻想をうち砕いてしまうが、しかし他方でそれは、資本主義が社会主義ないし共産主義の萌芽(ほうが)を自分のなかに秘めていること、そして資本主義は自然法則的な必然性で、また、それ自身の諸法則によって、社会主義ないし共産主義へと発展していかざるをえないことを証明しているので、明晰(めいせき)に物事を考えられるすべての社会民主主義者に、勝利へのゆるぎない確信を与えている」
これは『資本論』の核心を的確に述べていると思う。
モストの本は、『資本論』の単なる抜粋ではなく、わかりにくいところは言い換えて、重要な部分をわかりやすく労働者に伝えようとしている。たとえば、次のところだ。第1巻の第24章「いわゆる本源的蓄積」のむすびの部分、ここは資本主義から社会主義への移行はみんなが考えるほど困難で長期にわたるものではない、ということを語っているのだが、原文はかなり分かりにくい。それをモストは次のように言い換えている。
「分散的な所有の資本主義的所有への転化は、非常に長期にわたるものである。なぜなら、この場合に問題になったことは、少数の権力者による民衆の所有の取得だからである。(それと比べて)資本主義的所有の社会的所有への転換はもっと急速になしとげられる。なぜなら、この場合に問題になることは、民衆による少数の権力者……の排除だけだからである」
第2節 マルクス自身が加筆
モストの本は当時、『資本論』第1巻の内容を労働者に分かりやすく伝える唯一の手引き書だった。だからドイツ社会民主党の幹部は、マルクスに若干の加筆を要請した上で、76年に改訂第2版を発行した(この時、モストはパリ・コミューンをたたえた演説で再び逮捕され、投獄されていた)。私たちは今、この改訂第2版を読むことができる。
「商品と貨幣」「労働賃金」の章は、モストの要約ではまったく不十分であるとして、マルクス自身がほとんど全部書き直した。マルクスは、資本主義の理解のためには商品と貨幣、賃金についての正確な階級的認識が不可欠であり、ここを簡単にパスするわけにはいかないと思ったのだ。
ともあれマルクスが加筆して第2版が刊行されたことは、マルクスがモストによる要約を“これでよし”と認めたことを意味する。だから、私たちはモストの本を読むことで『資本論』第1巻の核心部分をつかめるのだ。
第4章 マル青労同・マル学同1千人組織建設の武器
第1節 「賃金」は奴隷の鎖
私がモストの『資本と労働』を読んで、強く印象に残ったところを記しておきたい。
賃金労働者は一切の生産手段を奪われているので、自分の労働力を資本家に売って賃金を得なければ生活できない。それを繰り返さなければ生きていけない。モストは、「賃金」が果たしているこの「鎖」の役割について、「検事・政治家・兵士たちの全部を合わせても、この形態すなわち労働賃金が果たしているほど大きな役割を果たしてはいない」と言っている。それほど強い力で「賃金」は労働者を資本家につないでいるということだ。
そして、続けてこう言っている。
「他の人間のために無償でおこなわなければならないどんな労働も、本来強制労働なのであって、この強制労働は、この人間が他の個々の人間なり、ある階級なりに対する隷属関係にあるということ、したがって彼は事実上奴隷であって、けっして自由人ではない、ということを示している」
この本当の事情が、労働賃金というありふれた形態によって覆い隠されるのだ。「外見上は、労働者は彼の労働のどの1分間といえども無償でおこなったわけではない。このように、彼の強制労働の、したがってまた彼の隷属関係の痕跡はあとかたもなく消えてしまっている」「ローマの奴隷は鎖によってその所有者につながれていたが、賃金労働者は見えない糸によってその所有者につながれている」
さらに、資本の生産過程は、資本と賃労働の階級関係そのものを再生産する過程である。
「資本主義的生産過程はそれ自身の進行によって、労働力と労働条件との分離を再生産する。したがってそれは、労働者の搾取条件を再生産し永久化する。それは、労働者には自分の労働力を売って生きていくことをたえず強要し、資本家にはそれを買って富をなすことをたえず可能にする」
「一方の極での資本の蓄積は、同時に反対の極での、すなわち自分の生産物を資本として生産する、まさにこの階級の側での困窮・労働苦・奴隷状態・無知・粗暴・道徳的堕落の蓄積なのである」
このようにモストは『資本論』第1巻のポイントを実に分かりやすく説いていく。学習会に格好のテキストだ。
マルクスは近代的資本の形成の歴史を、第1巻24章「いわゆる本源的蓄積」で、さまざまな歴史的事実を引いて克明に暴き出した。資本主義の成立過程が、資本家が言うような「勤勉に働いた者が財産をつくって資本家となり、怠け者が財産を失って無産労働者になった」というような「牧歌的」なものではけっしてないこと、イギリスの「土地囲い込み」による農民の暴力的追放や、各国が莫大(ばくだい)な利益を上げた奴隷貿易など、「征服や暴力」が資本の本源的蓄積の歴史的条件となったことを暴いた。
しかし、資本がおびただしい労働者の血を吸って大きくなっていることは、けっして過去の資本主義の生成期だけではない。マルクス当時も、そして今も同じだ。だから、資本についての断罪は、過去形ではなく現在形で書かれている。「資本は、頭からつま先まで、毛穴という毛穴から血と汚物とをしたたらせながら生まれてくる」
今、大恐慌のもとで、労働者に一切の犠牲を押しつけて延命を図る資本のありようを見た時、労働者の血と汗、あぶらを搾り取って生き続けようとする資本の本性は、まったく変わらないではないか。
第1節 革命の炎を広げよう
この書を締めるにあたって、モストは次のように言う。
「読者は、これまで抜粋によってお伝えしてきたマルクスの論述に教えられて、資本主義的生産様式はもともとひとつの過渡形態にすぎないこと、それはそれ自身の機構によって、もっと高度な生産様式に、協同組合的生産様式に、社会主義に行きつかないではいないのだ、ということをすでに認識されていることだろう」
「こんにちの社会はいずれ倒れて、もっと高度な、もっと高潔な社会に席を譲らないではいないのだという確信、そして労働者階級こそ政治権力という強大なテコによって現在の社会構造を根本的に変革する資格をもっているのだという確信、この確信をもった人ならだれでも、次のこと以外にいかなる生涯の使命をももつ必要がない。すなわち、自分の信条を他の人びとにも伝え、たえまなく宣伝の太鼓をたたき続け、全人類をきょうだいにするシンボル・赤旗のまわりに社会革命の兵士たちを次つぎに連れてきて、理想の達成をめざして燃えあがるような熱情を彼らの心に移植する、ということである」
「工場でも作業場でも、屋根裏部屋でも地下の住居でも、食堂でも散歩のときでも、要するに労働者のいるすべてのところで、宣伝が行われなければならないし、都市から農村へと認識が広められていかなければならない」「万国のプロレタリア、団結せよ!」
青年労働者モストの情熱は、いま革命をめざして闘う私たちの心にも熱いものを伝える。モスト『資本と労働』は、マル青労同1000人建設、マル学同1000人建設の重要な武器だ。学習しよう。そして、『資本論』そのものに挑戦しよう。マルクス主義と動労千葉労働運動で、圧倒的な労働者階級を組織し、組織し、組織しぬこう。
勝利はわれわれのものだ。
---------------------------
第1節 ●ヨハン・モスト略歴
1846年、ドイツ南部の古都アウグスブルクに生まれ、渡り製本職人として各地を歩いた。21歳の時スイスで社会主義的な労働運動に接し、25歳で社会民主労働者党に入党。情熱的な演説で繰り返し投獄された。労働者出身であることと投獄回数が多いことで労働者の尊敬を集めた。1872年9月、反戦デモを組織したかどで逮捕され、73年2月から8カ月間、ツヴィカウの監獄に抑留された。74年4月から再び26カ月間投獄された。ビスマルクの「社会主義者取締法」が発布されると、ドイツを追放されてロンドンに亡命した。社会民主党の指導部と対立し除名された。その後アメリカに渡り、1906年死去。